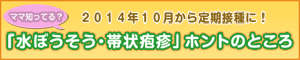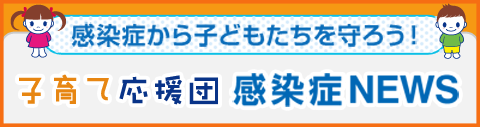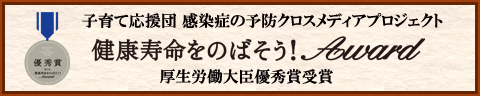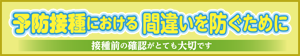【3月に注意してほしい感染症!】RSウイルス感染症堅調に増加 伝染性紅斑(りんご病)は増加の予測 医師「麻しんの患者発生状況を注視。3月以降も注意」
RSウイルス感染症とは?
RSウイルス感染症は、RS(respiratory syncytial)ウイルスを病原体とする、乳幼児に多く認められる急性呼吸器感染症です。主な感染経路は、患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手指や物品等を介した接触感染です。生後1歳までに50%以上の人が、2歳までにほぼ100%の人が1度は感染し、何度も感染するとされています。初感染の場合は発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、うち約20〜30%で気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現するとされています。乳幼児のおける肺炎の約50%、細気管支炎の約50〜90%の原因がRSウイルス感染症と考えられています。RSウイルス感染症には特効薬はありません。治療は基本的には対症療法(酸素投与、点滴、呼吸管理など症状を和らげる治療)を行います。
感染症に詳しい医師は…
感染症に詳しい大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長の安井良則医師は「RSウイルス感染症は、従来は春頃から流行が始まることが多く、今年のように年明けから流行が拡大していくというケースは過去にはありませんでした。現在は九州を中心に西日本で患者さんの報告数が多くあがっていますが、今後東日本に広がっていくと、流行がさらに拡大、長期化する可能性もあります。今までとは違う流行パターンなので、患者発生の推移は注意深く見守っていく必要があります」と語っています。特に感染しないように注意すべき人は?
感染によって重症化するリスクが高い人は、基礎疾患を有する小児(特に早産児や生後24か月以下で心臓や肺に基礎疾患がある小児、神経・筋疾患やあるいは免疫不全の基礎疾患を有する小児等)や、生後6か月以内の乳児です。また、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を有する高齢者も注意が必要です。特に生後1か月未満の乳児がRSウイルスに感染した場合は、非定型的な症状を呈するために診断が困難な場合があり、突然死につながる無呼吸発作を起こすことがあるので、注意して見守る必要があります。安井医師
「RSウイルス感染症は、大人や大きなお子さんが感染しても風邪のような症状しか出ませんが、乳児がかかると突然死など、命に関わる感染症です。乳児は症状が急変することもありますので、呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができない、あるいは機嫌が悪いなど小さなサインも見逃さないよう注意してください」
感染しないようにするには?
RSウイルス感染症の感染経路は接触感染と飛沫感染ですが、発症の中心は0、1歳児である一方、何度も感染したことがある年長児や成人では感冒様症状または気管支炎症状のみであることが多いことから、気づかずに乳幼児にうつしてしまうケースがあります。年長児や成人で風邪のような症状がある場合は、可能な限り乳幼児との接触を避けることが、乳幼児の感染予防につながります。接触感染対策としては、子どもたちが日常的に触れるおもちゃや手すりなどは、こまめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒し、流水・石けんによる手洗い、またはアルコール製剤による手指衛生が重要です。飛沫感染対策としては、鼻汁、咳などの呼吸器症状がある場合は、マスクが着用できる子どもや大人はマスクを使用することが大切です。
引用
国立感染症研究所:感染症発生動向調査週報2025年第11週(3/10〜16)、
厚生労働省HP:RSウイルス感染症Q&A(令和6年5月31日改訂)
取材
大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長 安井良則氏
国立感染症研究所:感染症発生動向調査週報2025年第11週(3/10〜16)、
厚生労働省HP:RSウイルス感染症Q&A(令和6年5月31日改訂)
取材
大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長 安井良則氏